ニュースでもよく取り上げられる高齢者の車の事故は死亡事故にもなりやすく、社会問題にもなっています。全体の交通事故の数は年々減ってはいますが、高齢者の事故の割合はまだまだ多いのが現状です。
後期高齢者の免許更新時には認知機能検査を受けることになり、以前に比べて免許返納の意識が高まってはいますが、実際に車がないと生活に不便な面も多く、少し無理をしてでも運転を続ける人は多いと思われます。
周囲の家族としては事故があってはいけないと、早めの免許返納を呼び掛けてはみたものの、本人の運転したい希望が強く、見守るしかない状況ということもあるでしょう。
今回は高齢者の運転事故の現状と原因、また運転をやめられない背景にふれながら、事故になる前に車の運転を検討する方法について解説しています。
ぜひ最後まで読んでいただき、安心したシニアライフに繋げていただければと思います。
高齢者の車の運転事故の現状

高齢者の運転についてニュース等でも事故の様子を取りあげられており、危ないイメージが強いでしょう。ここでは高齢者の運転事故の現状についてもう少し詳しく説明します。
高齢者の免許保有率は増加している
令和4年の65歳以上の高齢者の免許保有者は1946万人で全体の23.8%です。(警視庁交通局) 高齢者の人口が3620万人なので高齢者の半分以上の人が免許を保有していることになります。
特に事故のリスクが高くなる75歳以上の免許保有者が多く、10年前と比較して75歳以上は1.7倍、80歳以上は1.8倍の増化率になっています。
この高齢者の免許保有率の高さが全体の事故率は下がっても、高齢者の割合が高い大きな理由になっています。
高齢者の死亡事故の傾向
警察庁の発表した「令和4年における交通事故の発生状況について」によると免許人口10万人あたりの死亡事故数は、リスクが高くなる75歳以上で5.7、75歳未満で2.5となっています。75歳以上が2倍以上高く、やはり75歳以上の高齢者の運転についてある程度気を付ける必要があるでしょう。
また事故の内容についても75歳以上の高齢ドライバーは車両単独の事故の割合が多く、工作物衝突や路外逸脱が目立つ結果となっています。
高齢者の交通事故の主な原因

高齢化社会のなかで運転免許の保有率も年齢層が上がっていることが分かりました。特に75歳以上になると死亡事故率が急に上がるので特に注意が必要ですね。ここでは高齢者の交通事故の主な原因についてふれてみます。
運転技術の低下
高齢になるとどうしても関節の可動域が狭くなったり身体的に体が動かしにくくなり、運転技術にも影響がでることが多いです。
特に視力低下と聴力の低下によって情報の察知が遅れたり、反応時間が低下することにより、事故につながることもあります。
こうした高齢に伴う身体的な衰えは仕方ないことですが、つい自分の能力を過信してしまい、頭でできるつもりが体がついていけず結果的に事故になることもあるようです。
認知機能の低下
認知症高齢者による交通事故も問題になっていますが、高齢になると理解力や判断力が低下することで、交通事故を起こす可能性が高くなります。交通ルールが本人の頭のなかで曖昧になってしまい、周囲が思いもよらない運転をしてしまうこともあります。
例えば道路標識の認識の困難、交通量の多い場での判断力の低下などがあげられます。これらが事故リスクとしてかたちになると、逆走や急な車線変更となり、大きな事故につながってしまいます。
病気や薬の副作用
運転中に急に意識がなくなったり、体調の急変で事故につながることはニュースでも見たことがあると思います。これは誰にも起こるリスクではありますが、やはり高齢になればなるほどその確率は上がってしまいます。
また薬の副作用で眠気やめまい、しびれや視力低下等で運転に支障が出ることもあります。よく薬の注意書きで運転を控えるように記されていますが、特に高齢になると副作用も症状が大きくなりやすく、注意が必要です。
高齢者が運転を止められない理由

ここまで高齢者の運転の現状と事故が起こりやすい原因について説明してきました。ではなぜ高齢者は運転を続ける必要があるのでしょう。いくつか考えられる理由についてふれていきます。
買い物や通院などの移動手段
最も大きな理由は運転が生活に必要不可欠という移動手段になっていることでしょう。主に買い物や通院があげられ、車でないと荷物が運べないなど、大変不便を感じてしまうようです。
また公共交通機関を使う方法もありますが、その都度移動にお金がかかってしまうことを考えると車の運転を選択する人が多いかもしれません。
また地域によって公共交通機関が使いにくい土地もあり、都市部より地方や山間部に行くと公共バス等の便が乏しく、車以外の移動手段が考えにくいケースも多いです。
事故を起こさない自信がある
自分が事故を起こすはずがないと思っている高齢者が多いことも運転を続ける大きな理由でしょう。「長年運転していて自分の運転に自信がある」「自分にかぎって事故を起こすはずがない」と思う高齢者が多いアンケート結果もあります。
また運転を止めることで自分の生活が制限されたり、車の運転ができない喪失感から自信を失っていしまうと感じて、無理に続けている高齢者もいると考えられます。
特に運転免許証を保有しているのは男性が多く、運転することに固執する傾向があるのも男性の割合が高いようです。
趣味として運転をしたい
運転自体が楽しみである人はできるかぎり運転を続けたいと思うのはごく自然のことです。車の運転が趣味のようなものなので、生きる喜びを減らす行為は避けたいでしょう。
またドライブや旅行が趣味の人も車の運転がセットなので、なかなか止められないと思います。趣味は人生を豊かにする手段なので、簡単に手放せるものではありません。
高齢者に運転について考えてもらう方法

車の運転について何のために運転しているかで、考え方は変わってきます。ここでは運転している理由に合わせて具体的な検討方法を紹介していきます。
移動手段が理由の人の代替案
日常生活の中で買い物や通院は常に必要なので、車以外の移動手段について検討する必要があります。地域によってはコミュニティバスや乗り合いタクシーなどもやっているところもあるので一度自治体に問い合わせてみると良いでしょう。
また高齢者でも簡単に操作できる「シニアカー」の活用も検討できます。低速なので人身事故のようなリスクも低く、自分の好きなタイミングで外出できるのは魅力です。
自治体によっては免許返納したことで公共交通機関やタクシーが割引されたり、家族の車に同乗するだけでガソリン代が安くなる制度もあり、調べてみると意外なサポートが受けられるかもしれません。
運転が趣味の人の解決策
運転が好きな人は事故リスクの低い車を運転する工夫が必要になります。その方法の一つにサポートカー限定免許の取得があげられます。
サポートカーとは安全運転支援装置が搭載された自動車で、自動でブレーキが作動する衝突被害軽減ブレーキとペダル踏み間違い時における加速抑制装置がついているため、操作ミスによる大事故をある程度予防できます。
ただし対象の車に買い替える必要があるなど、大きな出費も発生するので簡単ではないかもしれません。アクセルとブレーキの踏み間違い事故は人の命に関わることもあるので、あとから後悔しないためにも必要な出費と捉えることもできるでしょう。
運転に自信がある人の運転適正チェック
客観的に自分の運転能力を知るためのツールを活用することが一つの方法です。自宅でもできるツールとしては警視庁が作成した「運転時認知障害早期発見チェックリスト」やJAFが作成した運転機能チェック&トレーニングツールなどがあげられます。
インターネットで検索するとすぐに試すことができるので、手軽に今の自分の運転能力を知るのに適しています。また免許センターや自動車学校でも高齢者の認知テストや運転能力のテストを行えますので活用してはいかがでしょう。
運転に対して自己判断ではなく、専門のツールやテストを受けることで客観的に自分の能力を知ることは事故を予防するために有効な方法でしょう。
さいごに

高齢になるとどうしても身体的、認知面の低下は進み、病気のリスクも大きくなります。それに伴って運転の事故リスクが上がることは、今回お伝えしました。
ただここで一番お伝えしたかったのは、高齢だから車の運転を控えたほうが良いというわけではなく、しっかり今のご自分の体の状況を理解し、適切な手段を検討することです。
運転技術が心配であれば、専門家の評価と助言を受けることもできますし、少しお金をかけてよければ自動ブレーキ付きの車に買い替えるのも一つの方法でしょう。
車の事故は誰も好きで起こすわけではありませんが、実際に事故を起こした場合、失うものはとても大きなものになります。
今回の記事を読んでいただき、安全な運転ライフを考えるきっかけになれば嬉しいです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
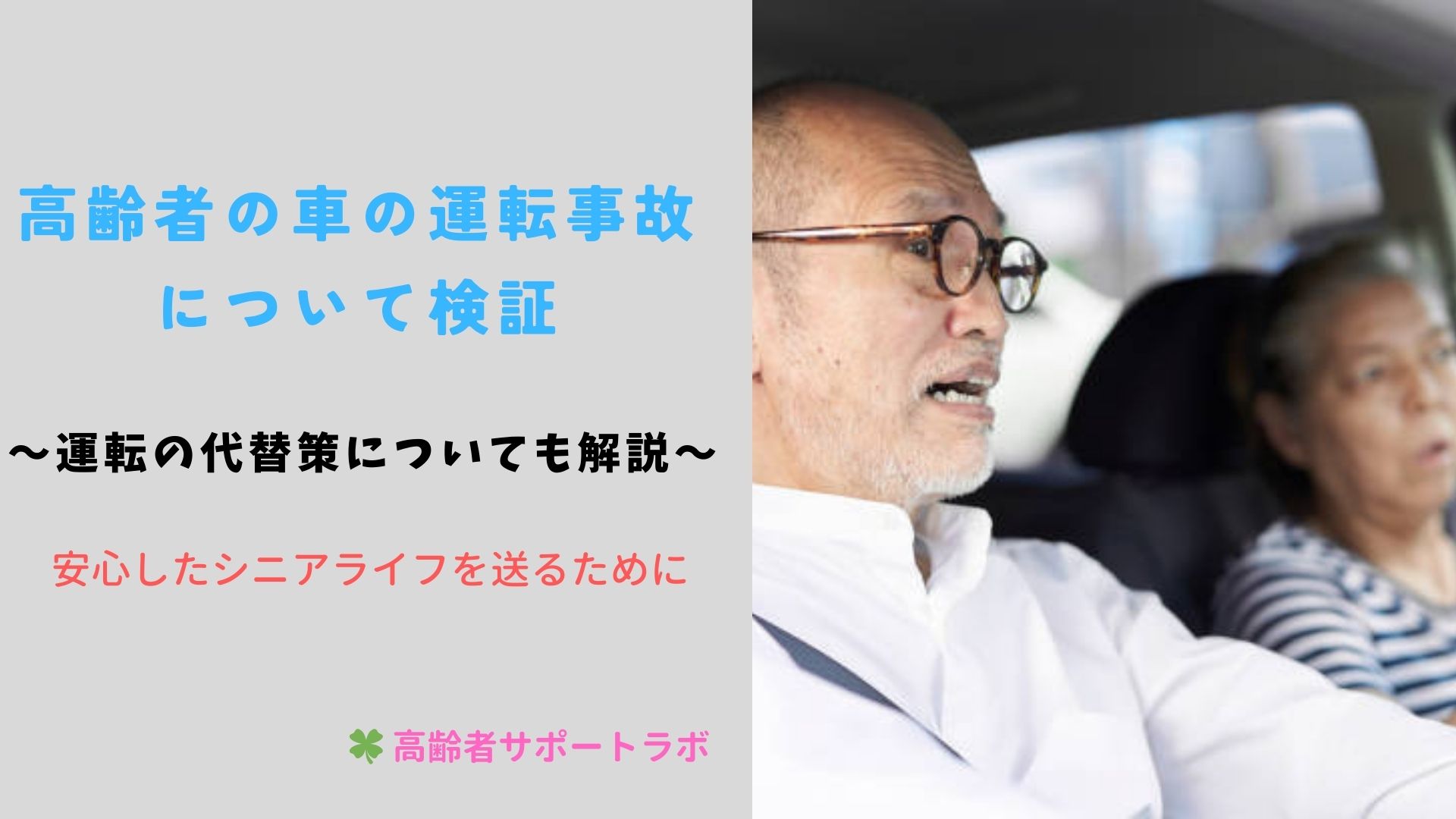


コメント